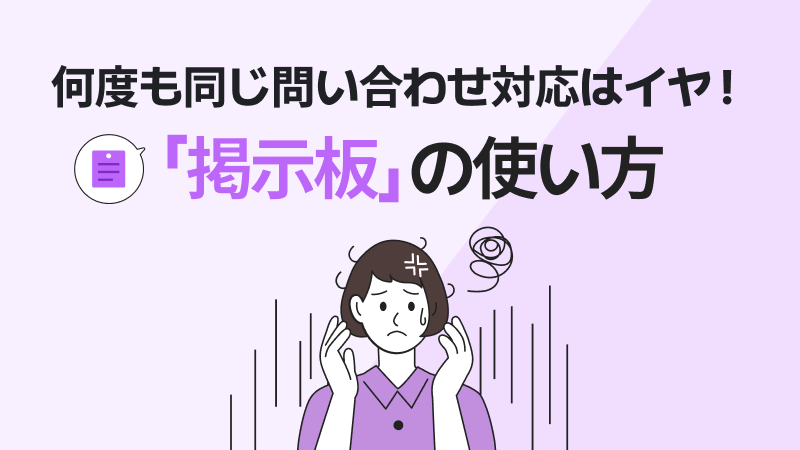9月は防災月間。
近年は猛暑や豪雨などの異常気象で全国各地に大規模災害が発生しています。防災は特別な準備ではなく、日常の習慣や人とのつながりがそのまま非常時の力になることもあります。
今回は熊本県球磨村役場の松本さんと、社会福祉法人球磨村社会福祉協議会(社協)の槻木さんに、球磨村での防災の取り組みや学びを伺いました。ファシリテーターはLINE WORKSアンバサダー(※)の長井さん。
“防災は日常の延長線”というテーマで、現場の声をお届けします。
※LINE WORKSアンバサダーとは、地域や業界の特性を理解し、「LINE WORKS」を積極的に活用しているユーザーで、LINE WORKS株式会社の社員から推薦を受けて認定されます。
LINE WORKS アンバサダー – LINE WORKS
プロフィール

長井 一浩
合同会社HUGKUMI(コンサルティング事業、研修事業)
社会福祉協議会の元職員。災害ボランティアセンターの運営支援や、社会福祉協議会などへのツール整備・活用アドバイスを担当。LINE WORKSアンバサダーとして、活用事例の紹介や導入サポートも手掛ける。

松本 憲吾
熊本県球磨郡球磨村役場 総務課 防災係
平成15年に球磨村役場に入庁。健康衛生課、住民福祉課、保健福祉課を経て、令和6年度より総務課防災係に配属。令和2年7月豪雨災害では、保健福祉課地域包括支援係として高齢者支援や介護予防事業、福祉避難所運営支援などに携わる。
球磨村役場の活動内容としては、令和2年7月豪雨からの復旧・復興に、熊本県や他県の職員とともに一丸となって取り組んでいる。
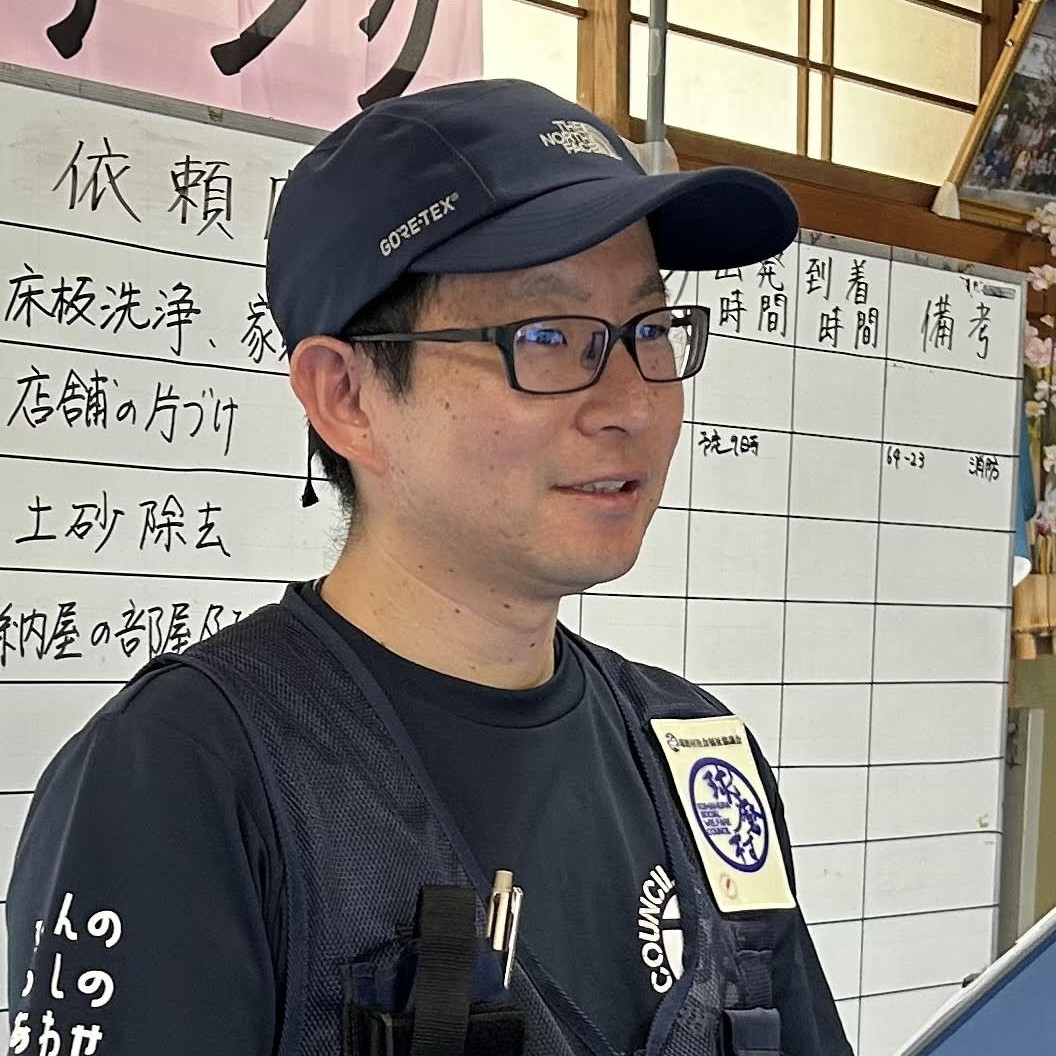
槻木 正剛
社会福祉法人球磨村社会福祉協議会
社協に勤務して18年目。地域福祉業務を担当。令和2年7月豪雨災害では、災害ボランティアセンターや地域支え合いセンターの設置・運営など、被災者支援に携わる。
球磨村社会福祉協議会の業務としては、住民からの様々な生活に関する相談窓口、福祉教育やボランティアの育成に取り組んでいる。
第1章:球磨村の防災は早めの行動から
長井:普段、球磨村ではどのように防災に取り組まれていますか?
松本:球磨村役場では、「災害が起きてからどのように動くか」ではなく、「起こる前にいかに早く動くか」を重視しています。気象庁から注意報や警報が発表された際の迅速な対応はもちろんですが、今後の雨量や雨雲の動きの予測、気象予報士の解説なども総合的に判断します。避難基準に該当した場合は、職員や消防団に連絡し、住民への声かけや避難準備を始めます。暗い中での避難は事故のリスクが高いため、明るいうちに行動することを心がけています。
長井:なるほど。球磨村では、早め早めに動くことがスタンダードなんですね。
松本:はい。結果的に安全ならそれでいい。住民の命が最優先です。
長井:早めの行動を支えるためには、情報共有や連携も重要だと思います。球磨村では、どのように職員や関係団体とコミュニケーションを取っているんでしょうか?
松本:以前は電話やメールが主流でしたが、情報の伝達に時間がかかったことをきっかけに、日常から使えるコミュニケーション手段として「LINE WORKS」が導入されました。平常時から用途に応じてグループを使い分け、リアルタイムで関係者全員に情報発信ができるので、即時性と正確性が格段に上がりました。
長井:日常で使い慣れているから、災害時にも迷わず活用できるんですね。
松本:はい。日常でのつながりや使い慣れがそのまま災害時の初動の速さにつながっています。

第2章:平常時の習慣が非常時を支える
長井:普段はどのように「LINE WORKS」を使っていますか?
松本:平常時は、課ごとにグループを作り、会議連絡や気象情報、住民から届いた意見などをトークで共有しているほか、掲示板で全体連絡も行っています。一斉に共有できるので情報の属人化も防げますし、日常的に使い込むことで、緊急時も操作に迷うことはありません。逆に言うと、平常時に使っていないものを緊急時に使うことは難しいと思います。使い方が分からない、誰にも聞けない…そのような状況になってしまいます。
長井:普段から使っているからこそ、災害時に迷わず使えるということですね。訓練はどのように行っているんでしょうか?
松本:そうですね、毎年実践的な訓練を行っています。訓練では、職員の参集や気象情報、災害対策本部の状況確認などに「LINE WORKS」を使用しています。過去に実際に災害も起こっていますので、定期的に訓練を行う重要性を感じています。
第3章:豪雨災害で見えた課題と学び
長井:令和2年7月に熊本県を中心に発生した豪雨災害では、球磨村も25名がお亡くなりになるなど甚大な被害を受けましたよね。その際はどのようにコミュニケーションを取られましたか?
松本:役場では、職員の安否確認や人員配置、避難者数、避難所当番、物資依頼などを「LINE WORKS」で一斉に連絡していました。情報が一元化されていたので、迅速に対応できたように思います。
長井:役場ではスムーズにコミュニケーションが取れたんですね。社協ではいかがでしたか?
槻木:社協では、発災直前・直後にはまだ「LINE WORKS」を導入していませんでした。行政からは避難所の情報をはじめ、通行止めなどの道路情報も届かず、電話もつながらない状況で職員や各団体との連絡が困難でした。そのため、避難所に行かなければならなかったのですが、距離が離れているため情報を聞いて戻って伝えるだけで1時間以上かかることもあり、もどかしさを感じたのを覚えています。
長井:私も当時、避難所に足を運びましたが、現場では刻一刻と状況が変わり、情報の速さと正確さが本当に求められていると実感しました。それだけ時間がかかると、どうしても対応が後手に回ってしまいますよね。
槻木:当時、行政の動きをリアルタイムで把握できる手段があれば、もっと体制を整えられたのではないかと感じました。こうした課題をきっかけに、社協でも「LINE WORKS」の導入が進み、非常時でも情報が常に入ってくるので、安心感がぐっと増しました。例えばコロナ禍の避難所対応では、発熱者が出た際に看護師へ即座に連絡するなど、現場の対応力が大きく高まったと実感しています。
長井:役場と社協でツールを活用し、情報共有が進むことで、住民の安全もより確実になったわけですね。
槻木:そうなんです。社協では被災された方々への支援や見守り、コミュニティ構築やボランティア団体の活動調整などを行う地域支えあいセンターを運営しています。地域支えあいセンターでは、豪雨災害で被災した約200世帯の見守りに「LINE WORKS」を活用し、被災者からの問い合わせにもその場で対応できています。
長井:非常時の対応力が大きく高まったことが伝わってきます。一方で、当時の経験を通して見えてきた課題にはどんなものがありましたか?
槻木:一番大きかったのは、通信環境が整わない状況です。基地局や電気の停止で電話やインターネットが使えず、外部と連絡が取れない時間がありました。そのため、ツールの便利さを十分に活かせない状況もありました。
長井:ツールを導入することも重要ですが、ツールが使える通信環境を整備すること、そして災害や想定外の事態が起きたときにどう対応するかを事前に決めておくことの重要性を改めて実感しますね。


第4章:これからの防災への取り組み
長井:今後は、どのような防災への取り組みを進めていきたいですか?
松本:役場としては、平常時からツールの機能を理解し、職員全員がさらに活用できるよう習熟度を高めていきたいと思います。また、全国的に「LINE WORKS」を活用する団体も増えていると聞いたので、このネットワークを活かせば災害時の情報共有や支援体制もさらに強化できそうだと感じました。
槻木:社協としてのBCP(事業継続計画)を整備し、大規模災害時も安定した支援を提供できる体制を確立していきたいと考えています。現地でのボランティア活動では、被災者が立ち合いできない場合や、移動が困難な場合があります。その際に「LINE WORKS」の動画・画像共有機能を活用することで、直接足を運ばなくても、現地活動のボランティアや職員とスムーズに連絡を取れる仕組みができると、被災者の負担も大きく軽減できると思います。
長井:平常時からの行動が、防災の安心につながる――まさに本企画のテーマですね。
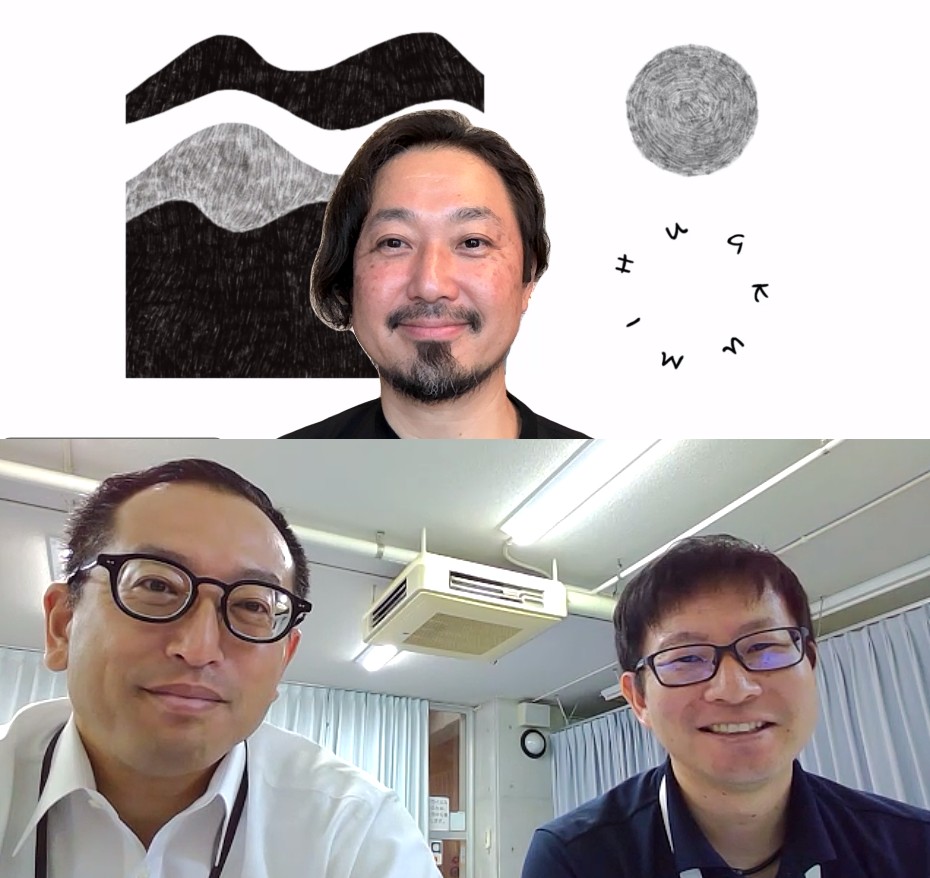
最後に
今回のお話から見えてきたのは、防災が「特別な準備」ではなく、まさに「日常の延長線」にあるということです。
球磨村役場が実践している早めに動く姿勢や、社協が学びを経て取り入れたICTの活用。そうした日常の積み重ねが、災害時の確実な初動の速さや住民の安心につながっていました。
防災月間をきっかけに、皆さんもぜひ「日常での当たり前を非常時にどう活かすか」を意識してみてはいかがでしょうか。
LINE WORKSの製品導入をご検討の方はこちらから
LINE WORKS | LINEとつながる唯一のビジネスチャット
非営利団体様向け特別プランはこちらから
非営利団体向け特別プラン提供キャンペーン ー LINE WORKS