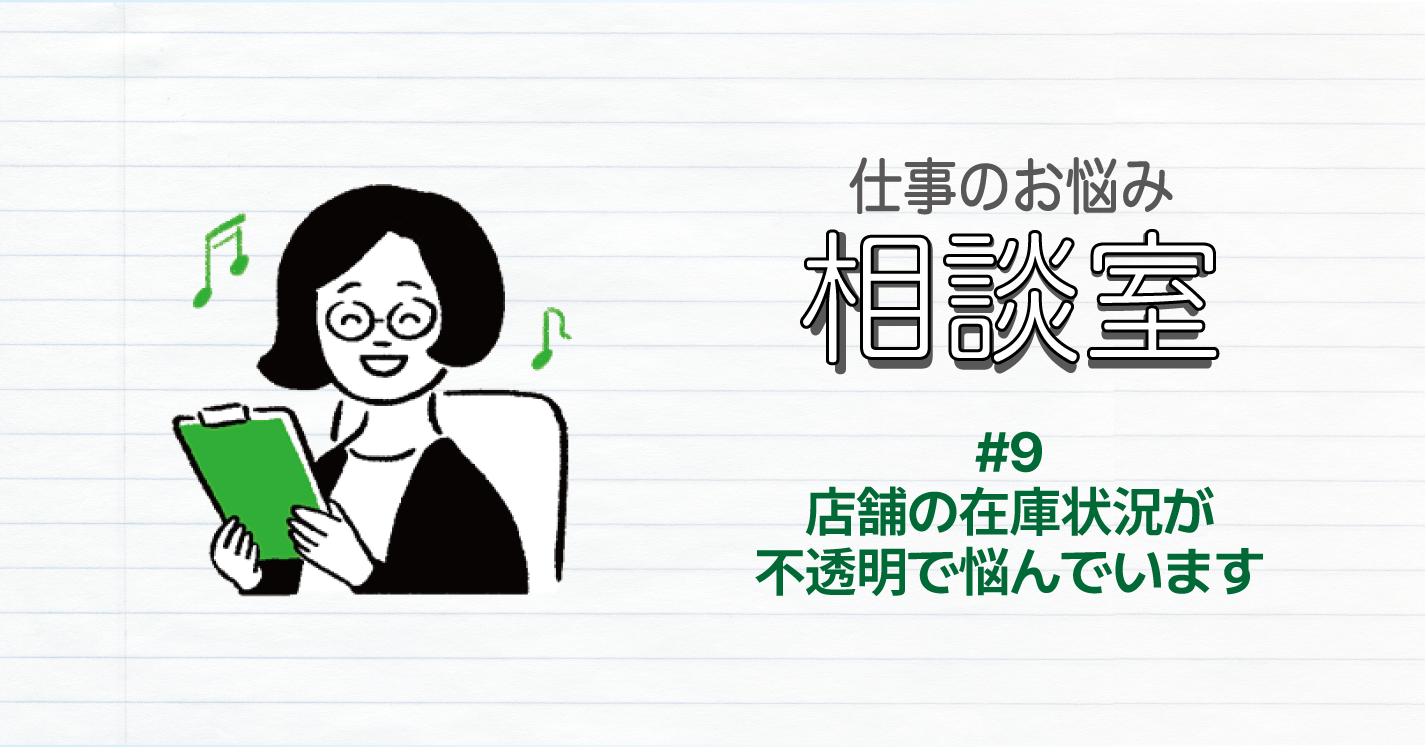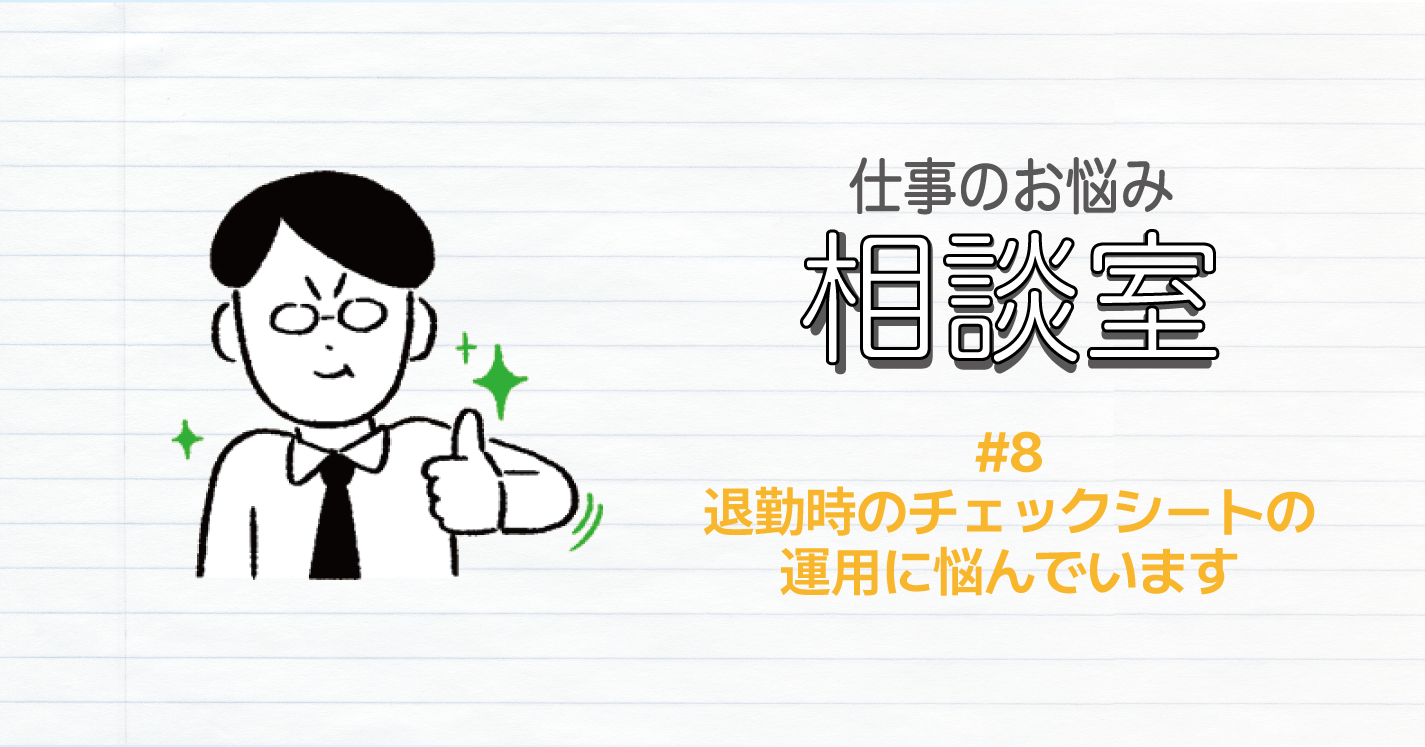2025年3月25日、4月1日より導入されるLINE WORKSを活用した救急隊と病院が連携するアプリ「スクエル」の説明会が開催されました。この説明会には消防職員や医療従事者を中心に約80名が参加し、「スクエル」の導入経緯や活用方法、トライアル運用後のフィードバック、そして今後の取り組みについて説明が行われました。
■開会の挨拶
開会の挨拶では、消防長の中田様が「スクエルを活用して、搬送を円滑かつ的確に行い、一人でも多くの命を救いたい」と参加者へ想いを述べました。続いて、救急DX環境構築プロジェクトチームの皆様からは、スクエル導入の経緯と今後の活用方法について説明がありました。

小山市消防 消防長の中田様からのご挨拶
■スクエル導入の背景
昨今、救急出動件数や搬送人員の増加が続いており、現場滞在時間も年々長くなっています。その一因として、病院の収容不能が挙げられます。例えば、ベッドの満床や手術・処置中のため受け入れが難しい病院が多く、救急隊が現場で長時間滞在する事例が増加しています。この問題に対応するために、「LINE WORKS」を基盤に麻生情報システムが開発を行なった「スクエル」が導入されることになりました。「LINE WORKS」は、LINEに似た使い勝手を持ち、簡単に操作できるため、幅広い年齢層に対応可能で、さらにセキュリティ面でも安心して使用できるため、導入が進められました。
■トライアル運用とフィードバック
実際にトライアル運用を行った結果、医療従事者からは「画像共有ができることで、状況がわかりやすい、収容依頼を受けた事務員も医師に説明しやすい」といった意見が寄せられました。また、救急隊からも「件数が少ないものの、操作に慣れれば非常に有効だ」との感想がありました。今後も、ユーザーからのフィードバックをもとに改良を重ね、より使いやすいシステムにしていくことが目指されています。
■スクエルの活用
スクエルの最大の強みは、複数の病院に対して一度に受け入れ可否を確認できる点です。従来、病院に照会する際は、1回あたり平均14分がかかり、照会回数が増えるごとにその時間も長くなります。しかし、スクエルを使えば、1回の照会で複数の病院の受け入れ状況を確認でき、受け入れ不可の理由も共有されるため、次の病院に照会する必要がなくなります。この効率化により、救急隊が迅速に最適な受け入れ先を見つけることが可能になり、搬送困難な状況を減らすことを目指しています。

説明会の様子
■今後の展望
今後、救急出動件数が増加し、搬送困難が発生しやすくなる時期、特にインフルエンザなどの流行時に、スクエルを使って迅速に医療機関を探し、患者の搬送を円滑に行うことが求められます。現状では受け入れ先の医療機関が不足しており、県外への搬送が発生することもあります。地域ごとに異なる連絡方法を統一するため、スクエルが共通のプラットフォームとして活用されることが期待されています。
■DX化の進展と今後の期待
菅原様は、DX化を進める際の最大の障壁として「事業費用」が挙げられると述べられました。ただ、今回は国からのデジタル田園都市国家構想交付金により、事業費の半額が補助される形で推進できたことを明らかにしました。DX化を推進するにあたり、アプリケーションの開発費がもっともかかると思います。その中で、今回我々が導入したスクエルのプラットフォームを多くの地域でも提供されたら、開発費用が抑えられる点でも大きなメリットになると考えています。今後、さらに多くの地域でスクエルを活用し、救急隊と病院の連携が強化されることが期待されています。

インタビューを受けてくださった救急DX環境構築プロジェクトチームの菅原様
■おわりに
救急対応において、リアルタイムでのコミュニケーションや情報の共有が非常に重要です。「LINE WORKS」を活用した「スクエル」は、その課題に取り組むための強力なツールとなり、救急医療の効率化と質の向上の実現を目指しています。今後もLINE WORKSは麻生情報システムとの連携を強化し、救急現場を含めた現場の迅速な対応にも貢献すべく、サービスの改善などの取り組みを継続してまいります。